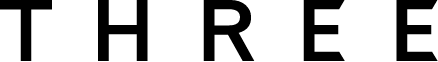プロローグ

私は主に、星占いの記事を書くことを生業としている。
星占いの記事の多くは、女性向けのファッション誌に掲載される。
ゆえに、最近では化粧品や美容関係のメーカーさんなどから「PR誌に、美についての記事を書いて頂けませんか」というご依頼を、よく頂くようになった。
が、私は「美」について、何も知らない。
かつて美少女だったことも美女だったこともなく、常に「男に生まれていたらどんなによかったか」と思いながら、自分の女性性と無益な戦いを続けるという半生を送ってきたため、美容とかお化粧とかいうことについて、ほとんど知識が無いのである。
したがって、「美についての記事を」とのご依頼には、「美のことは全然解らないので」とお断りするほかなかった。
しかし。
「美」とは、いったいなんなのだろう。
このことは、職業上、イヤでもたまに、考えざるを得ない。
というのも、星占いは主に、「悩める人々」のものである。
悩みや迷いのないところに、占いは(ほとんど)必要ない。
多くの悩める女性たち、否、性別を問わず、愛に悩む人々が「美しくなりたい」という問題意識を抱えている。美しくなれば、人から愛される。自分は美しくない、だから、愛されない。この痛烈な悩みは、大昔から途絶えることがない。
一方で、美しい容姿を持つことで悩んでいる人もいる。多くの人を惹きつけることから生まれる悩みは多いらしい。嫉妬、無視される人間性、望まぬトラブル等、美貌が人間関係に影を落とすことはめずらしくない。実際、素晴らしい美貌の持ち主が、必ず愛されて幸せになっているかというと、そうでもない。むしろ、「薄幸の美女」という表現があるが、壮絶な転落の人生を辿る例も多々ある。
美と幸福、美と人間関係は、切っても切れないテーマなのだ。

どんな条件が揃っていれば「美しい」のかは、文化によって異なる。 以前、テレビのある番組で、日本の有名人の写真を数枚フリップに並べ、「いちばん美女だと思えるのはどれか」をモンゴルの人々に選んでもらう、という企画があった。すると、藤原紀香さんなど並みいる美人女優を抑えてダントツに人気があったのは、タレントの山田花子さんの写真であった。
「美」は、一体何でできているのだろうか。
また、私たちが「美」にもとめているのは、どんなものなのだろうか。 このことを考える時、その入り口で、必ず思い浮かぶ言葉ある。 それは、過去に何度か引用してきたフレーズだ。
「明朗な心と、清新な感覚と、素直な清らかな情熱を老年まで保っている婦人は、たいていは若く見えるものだ。ついでに言うが、これらすべてのものを保つことが、おばあさんになってからも自分の美しさを失わないたった一つの方法である。」
「若さ」と「美しさ」が、全く別のものとして語られている。一般に、「若さ」イコール「美しさ」として語られることが多いが、文豪はその厳然たる違いを見抜き、注意深く切り分けて扱っているのだ。
これはドストエフスキー「罪と罰」(新潮社)の中の一節で、主人公の大学生ラスコーリニコフの母、プリへーリヤ・アレクサンドロヴナの描写である。
彼女はこのとき 43歳で、現代的にはまだまだ若い年齢だが、当時の感覚では既に中年から老境にさしかかるころなのだろう。
このフレーズのあとに、彼女についての描写がこんなふうに続く。
「髪にはもう白いものがまじり、うすくなりかけていたし、目じりにはもうかなりまえからちりめんのような小じわがあらわれ、気苦労と悲しみのために頬はおちて、かさかさになってはいたが、それでもその顔は美しかった。」
白髪、薄くなった髪、小じわ、こけた頬、乾いた肌。
これらは、「美容」の世界では、ほとんど恐怖の的である。
ゆえに、これらを逃れるための手だてがたくさん提供されている。カラーリング、植毛やウィッグ、しわをなくし潤いを保つためのさまざまな化粧品、「内側から美しくなる」ための食事、サプリメント。
しかし、ドストエフスキーが描いたこの女性は、そんな手だては一切無くても「その顔は美しい」と述べている。
いったい、私たちはそうした顔を見たことがあるだろうか。
そうした「美しい顔」を思い浮かべることができるだろうか。
さらに、彼女の人柄については、こう続く。
「プリヘーリヤ・アレクサンドロヴナは涙もろいが、それもいやらしいほどではなく、気が弱く従順だが、それにも程度があった。」「…彼女にはまことと、いましめと、ぎりぎりの信念の最後の一線があって、どんな事情も彼女にその一線をこえさせることができなかった。」
一般に「女性らしさ」に分類される、従順さや涙もろさの一方で、絶対に越えさせられない一線という「頑固さ」が彼女にはあるということだろうか。あるいは「頑固さ」ではなく、「潔癖さ」「節操の硬さ」とでもいおうか。または「誠実さ」「信念への忠実さ」とも呼べるかもしれない。
ここでは「変わるもの」と「変わらないもの」の対比が何度も繰り返されている。
すなわち、小じわや抜け毛、白髪などで「若さ」は失われる。悲しみや苦労によって、生き生きした明るさは失われる。しかし、その一方で、失われない「美しさ」がある。従順さや涙もろさは運命に翻弄されるが、その一方で、決して越えることのできない清らかな信念の一線は、運命と闘う力を持つ。
変わるものの中にある、変わらないもの。
この「変わらないもの」の中に、ドストエフスキーは「自分の美しさ」を挙げている。
単なる「美しさ」ではなく、「『自分の』美しさ」としたのは、なぜだろう。
誰にでも「自分固有」の美しさがあって、いつまでも失わずにいられるのはそれだけだ、ということなのだろうか。
であれば、それはどのように作られるのだろうか。

「内面が清らかならば、外面も美しく見える」というような単純な「因果関係」を想定するのは、乱暴だろう。文字通りの「すがたかたち」の美しさというものは、厳然として、存在する。
しかし、私たちはもうひとつのことを、誰に教わりもしないのに直観している。
それは、「『美』は生まれ持ったすがたかたちや、いわゆる『美しくなるための努力』だけで出来ているものだろうか?」という疑いである。
この直観的疑いを出発点として、この連載では、小説他、さまざまな場に描かれる「美」や「美人」の姿を通して、「美」が私たちにとってどういう意味を持ちうるのかを、考えてみたいと思う。
通常「美」についてのコラムは、美を愛する人や、美に関する仕事に携わる人や、すでに美しいと認められている人や、美のために努力を重ねてきた人などが書くものだろうと思う。が、この稿は違う。
「美」をあきらめて「美」から遠ざかり続けて来た私が、遙か彼方を遠く見晴るかすようにして、言葉の世界から「美」を考えるとどうなるか、そのあたりをお楽しみいただければありがたい。
> #002 美は「見いだされる」。