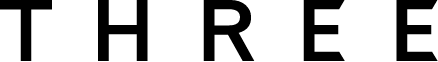先日、ティアラのデザインを仕事にしている、紙谷太朗さんという方にお目にかかる機会があった。聞けば、この連載を読んで下さったという。「美」について書いている本連載だが、結婚式に新婦が身につけるティアラを作る紙谷さんにとって、「美」はとても重要なテーマであるらしい。
紙谷さんは、オーダーメイドでティアラを作っている。それも、顧客の「こういうのを作って欲しい」という要望通りにつくるのではない。新婦がどんな女性なのか、あるいは、結婚式においてどんなことを表現したいのか、そうしたことを詳しくヒアリングし、そのテーマに沿ったティアラを「クリエイト」するのである。彼の作るティアラは、新婦やそのカップルを「表現したもの」で、ある種の「結晶」のようなものなのだ。
ゆえに、紙谷さんは女性や人間の「美しさ」に注目する。
彼はそういう経験と問題意識の中で、「心を動かす」ものが「美」だと言った。

「すがたかたちの美しさも当然、人の心を動かします。美しいな、好きだな、というのも『情』です。でも、人の心が動くのって、それだけではないですよね。ある研究では、結婚して長い年月いっしょにいる夫婦は、いくら憎み合っていても、第三者が下すのと比べて、相手を高く評価する傾向があるんだそうです。それはつまり、そこに『情』があって、それで相手が美しく見えている、ということなんです」。
たとえば、ある女性がいるとする。
この女性を、長年連れ添った夫と、第三者である男性に、別々に評価してもらうと、かならず、長年連れ添った夫の方が「好評価」を下す、というのだ。
たとえ夫婦がもう、(自覚的には)愛し合っていなかったとしても、だ。

私たちは、見知らぬ他人に「美しい」と思われたいと願っている。だが、もっと言えば、愛する人や親しい人から「美しい」と思われたい気持ちは、もっと強いのではないだろうか。
紙谷さんの話によれば、慣れ親しみ、ひとたび「情」を動かされた相手の顔は、他人が見るよりも、更に美しく見えている、ものらしい。もしそれが本当なら、「美しさ」は、客観的なものではないのだろう。
「美しさ」が主観に過ぎないなんて、誰でもわかる、と思われるだろう。たとえば、一人の女優さんを熱愛するファンが大勢いるかと思えば、毛嫌いしている一派が存在したりする。彼女を愛する人も、嫌っている人も、「自分は客観的に評価している」と感じている。あるいは「自分は単なる主観で彼女を好きなのだ」と自覚していたとしても、その主観には「ある程度以上に、普遍性がある」と考えていることが多いように思う。
でも、私たちが自分の容姿に「自信が持てない」と感じる時、「自分は客観的に自分の美醜を判断している」と信じている。「誰が見ても自分を美人だなどとは言わないだろう」と信じている。
しかしそれは間違っている。
なぜなら、現実には、「誰が見てもこのように見える」という顔は、ないからだ。
美醜に、「客観」は、ないのだ。

ふと思いついて、私は紙谷さんに、こんなことを聞いてみた。
「もし、非の打ちどころのないような、内面も外面も完全に美しい人がいたら、紙谷さんは、ティアラをつくりたいと思いますか?」
紙谷さんは、これに、即答した。
「作らないですね、だって、要らないですよね」。
この答えは、私の予想とぴったりだった。
でも、どうして、そうなるのだろう。
この件は、次回に。
※本文中のティアラ・デザイナーの紙谷太朗さんと石井ゆかりさんのお話は、Webマガジン「ミシマガジン」の「闇鍋インタビュー」でご覧いただけます。
> #004 「部分」としての美、「動き」としての美。

 「すがたかたちの美しさも当然、人の心を動かします。美しいな、好きだな、というのも『情』です。でも、人の心が動くのって、それだけではないですよね。ある研究では、結婚して長い年月いっしょにいる夫婦は、いくら憎み合っていても、第三者が下すのと比べて、相手を高く評価する傾向があるんだそうです。それはつまり、そこに『情』があって、それで相手が美しく見えている、ということなんです」。
たとえば、ある女性がいるとする。
この女性を、長年連れ添った夫と、第三者である男性に、別々に評価してもらうと、かならず、長年連れ添った夫の方が「好評価」を下す、というのだ。
たとえ夫婦がもう、(自覚的には)愛し合っていなかったとしても、だ。
「すがたかたちの美しさも当然、人の心を動かします。美しいな、好きだな、というのも『情』です。でも、人の心が動くのって、それだけではないですよね。ある研究では、結婚して長い年月いっしょにいる夫婦は、いくら憎み合っていても、第三者が下すのと比べて、相手を高く評価する傾向があるんだそうです。それはつまり、そこに『情』があって、それで相手が美しく見えている、ということなんです」。
たとえば、ある女性がいるとする。
この女性を、長年連れ添った夫と、第三者である男性に、別々に評価してもらうと、かならず、長年連れ添った夫の方が「好評価」を下す、というのだ。
たとえ夫婦がもう、(自覚的には)愛し合っていなかったとしても、だ。
 私たちは、見知らぬ他人に「美しい」と思われたいと願っている。だが、もっと言えば、愛する人や親しい人から「美しい」と思われたい気持ちは、もっと強いのではないだろうか。
紙谷さんの話によれば、慣れ親しみ、ひとたび「情」を動かされた相手の顔は、他人が見るよりも、更に美しく見えている、ものらしい。もしそれが本当なら、「美しさ」は、客観的なものではないのだろう。
「美しさ」が主観に過ぎないなんて、誰でもわかる、と思われるだろう。たとえば、一人の女優さんを熱愛するファンが大勢いるかと思えば、毛嫌いしている一派が存在したりする。彼女を愛する人も、嫌っている人も、「自分は客観的に評価している」と感じている。あるいは「自分は単なる主観で彼女を好きなのだ」と自覚していたとしても、その主観には「ある程度以上に、普遍性がある」と考えていることが多いように思う。
でも、私たちが自分の容姿に「自信が持てない」と感じる時、「自分は客観的に自分の美醜を判断している」と信じている。「誰が見ても自分を美人だなどとは言わないだろう」と信じている。
しかしそれは間違っている。
なぜなら、現実には、「誰が見てもこのように見える」という顔は、ないからだ。
美醜に、「客観」は、ないのだ。
私たちは、見知らぬ他人に「美しい」と思われたいと願っている。だが、もっと言えば、愛する人や親しい人から「美しい」と思われたい気持ちは、もっと強いのではないだろうか。
紙谷さんの話によれば、慣れ親しみ、ひとたび「情」を動かされた相手の顔は、他人が見るよりも、更に美しく見えている、ものらしい。もしそれが本当なら、「美しさ」は、客観的なものではないのだろう。
「美しさ」が主観に過ぎないなんて、誰でもわかる、と思われるだろう。たとえば、一人の女優さんを熱愛するファンが大勢いるかと思えば、毛嫌いしている一派が存在したりする。彼女を愛する人も、嫌っている人も、「自分は客観的に評価している」と感じている。あるいは「自分は単なる主観で彼女を好きなのだ」と自覚していたとしても、その主観には「ある程度以上に、普遍性がある」と考えていることが多いように思う。
でも、私たちが自分の容姿に「自信が持てない」と感じる時、「自分は客観的に自分の美醜を判断している」と信じている。「誰が見ても自分を美人だなどとは言わないだろう」と信じている。
しかしそれは間違っている。
なぜなら、現実には、「誰が見てもこのように見える」という顔は、ないからだ。
美醜に、「客観」は、ないのだ。
 ふと思いついて、私は紙谷さんに、こんなことを聞いてみた。
「もし、非の打ちどころのないような、内面も外面も完全に美しい人がいたら、紙谷さんは、ティアラをつくりたいと思いますか?」
紙谷さんは、これに、即答した。
「作らないですね、だって、要らないですよね」。
この答えは、私の予想とぴったりだった。
でも、どうして、そうなるのだろう。
この件は、次回に。
※本文中のティアラ・デザイナーの紙谷太朗さんと石井ゆかりさんのお話は、Webマガジン「ミシマガジン」の「闇鍋インタビュー」でご覧いただけます。
> #004 「部分」としての美、「動き」としての美。
ふと思いついて、私は紙谷さんに、こんなことを聞いてみた。
「もし、非の打ちどころのないような、内面も外面も完全に美しい人がいたら、紙谷さんは、ティアラをつくりたいと思いますか?」
紙谷さんは、これに、即答した。
「作らないですね、だって、要らないですよね」。
この答えは、私の予想とぴったりだった。
でも、どうして、そうなるのだろう。
この件は、次回に。
※本文中のティアラ・デザイナーの紙谷太朗さんと石井ゆかりさんのお話は、Webマガジン「ミシマガジン」の「闇鍋インタビュー」でご覧いただけます。
> #004 「部分」としての美、「動き」としての美。