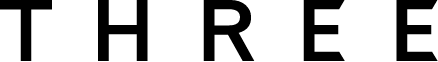「ハマのメリーさん」と呼ばれた人がいる。
既に故人だが、私はこの女性をある写真集で知った。荒木経惟氏の「恋する老人達」だ。しどけなくベッドに横たわってパイプをくゆらせる、濃い化粧をした老女の姿がモノクロームで写し出されていた。
彼女がどういう人物なのか知らなかったのだが、最近になって彼女に関する映画作品があることを知った。タイトルは「横浜メリー」。すぐにあの「メリーさん」が思い当たった。横浜でメリーさんと接していた人々へのインタビューを軸に構成された、ノンフィクションだった。
「横浜メリー」「ハマのメリーさん」と呼ばれたその女性は、日本人である。
戦後、横浜の街には米兵相手の街娼がたくさんいた。メリーさんもその一人であった。彼女の語るところによれば、若い頃あるアメリカ人将校と激しい恋に落ちた。彼女はその恋にすべてを賭けて、老女となった今も彼を待ちながら横浜で街娼を続けている、というのだった。街娼時代、仲間の娼婦達からは「お高くとまっている」「つんとしている」と言われた。いつも一人で行動し、娼婦達の賑やかなお喋りに加わることはなかった。

1995年くらいまで、彼女はクラシックな真っ白いドレスに身を包み、丁寧に化粧を施して、横浜の街角にあくまで街娼として立ち続けた。誰が見ても、歴とした「老女」である。ゆえに、お客がつくことはほとんどない。時折、昔なじみが幾ばくかのお金を手渡していたようだった。
その暮らしは、最後のほうはほぼホームレスに近かった。荷物をクリーニング屋さんに預け、決まった美容院に出入りし、昼間から夜、横浜の街を徘徊する日々。真っ白に着飾った老女がうろうろと街中を歩き回る姿は異様で、彼女は有名人だった。じろじろ見られたり、嗤われたり、店やビルからつまみ出されることも珍しくなかった。しかし彼女は超然として、決して自分が自分である事をやめなかった。
印象的だったのは、ある化粧品店のスタッフの証言だ。
メリーさんはしばしばその化粧品店にいりびたり、なにを買うでもなくしきりに、輸入化粧品や香水の美しい瓶に魅入っていた。色とりどりのガラス瓶に見とれては、きれいねえ、きれいねえ、と呟いていたという。美しい化粧品の瓶に幻影を見る、空想力と美意識が、彼女の頭の中には常に躍動していたのではないか。美しい恋、美しいドレス、美しいドラマ。彼女は誰にも見えない自分だけの美の世界を、かたくなに行き続けていたのではないか。
滑稽にも哀れにも思える彼女の生き方が、その足跡を辿るうち、だんだん違ったものに見えてくる。人は、そんなにもかたくなに「自分自身でいる」ことが、できるものなのだろうか。他人がどう思おうと、彼女は自分の美と愛に忠実に生きたのだ。映画が進むにつれて、玉葱の皮を剥いていくように、透き通るように純粋な「美しい」生き方が姿を現す。

ある救急隊員の手記として、こんな記事を読んだことがある。
119番の要請に応じて夜中、ある家に駆けつけた。倒れたのは70代になる女性で、意識を失いかけている状態だった。担架に乗せると、彼女はほぼ意識の無い状態のまま、着ていた寝間着の裾を直そうとしたのだという。
救急隊員の青年はその仕草に、痛烈な「女性」を感じて、衝撃を受けた、と語った。その衝撃には、尊敬のような、畏怖のような、「頭の下がる思い」が含まれていたようだった。
実は、本連載の最終回は、「美とは○○である」というふうに、警句的な一文で締めたいと思っていた。しかし書き進めるうちに、この2つのエピソードが常に私の頭に、「美」のベース音のようにしてこびりついているのに気がついた。
美しくあるためには、何が美しいのかということをまず、知らなければならないのだろうと思う。でも、万人に共通の、教科書のような美というものはない。
かつて中国で小さな足が美しいという観念が広まり「纏足」が流行したと歴史で習った。しかし最近まで、私は「纏足」が実際にどんなものなのか、全く知らなかった。「纏足」とは、幼女の足指の骨を折ってしまい(!)、きつく布で巻き締める、という風習だったのだ。インターネットで検索すると、画像が出てくるので、ご興味の向きは是非、参照されたい(かなりショッキングなものなので、ご注意を)。
私たちが心のどこかで望んでいる美というのは、そんなものではないはずだ。
ならば、何を美とするのか。

美しくなれる薬があり、美しくなれる化粧品があり、美しくなれる服がある。少なくとも、そう考えられている。しかし、その中のどれを選べば良いのか、ということへの答えは、どこにもない。
多分、その答えを「自分以外の誰か」に求めているうちは、なかなか、「美」には近づけないのかもしれない、と私は思っている。
> 「美人の条件」記事一覧

 1995年くらいまで、彼女はクラシックな真っ白いドレスに身を包み、丁寧に化粧を施して、横浜の街角にあくまで街娼として立ち続けた。誰が見ても、歴とした「老女」である。ゆえに、お客がつくことはほとんどない。時折、昔なじみが幾ばくかのお金を手渡していたようだった。
その暮らしは、最後のほうはほぼホームレスに近かった。荷物をクリーニング屋さんに預け、決まった美容院に出入りし、昼間から夜、横浜の街を徘徊する日々。真っ白に着飾った老女がうろうろと街中を歩き回る姿は異様で、彼女は有名人だった。じろじろ見られたり、嗤われたり、店やビルからつまみ出されることも珍しくなかった。しかし彼女は超然として、決して自分が自分である事をやめなかった。
印象的だったのは、ある化粧品店のスタッフの証言だ。
メリーさんはしばしばその化粧品店にいりびたり、なにを買うでもなくしきりに、輸入化粧品や香水の美しい瓶に魅入っていた。色とりどりのガラス瓶に見とれては、きれいねえ、きれいねえ、と呟いていたという。美しい化粧品の瓶に幻影を見る、空想力と美意識が、彼女の頭の中には常に躍動していたのではないか。美しい恋、美しいドレス、美しいドラマ。彼女は誰にも見えない自分だけの美の世界を、かたくなに行き続けていたのではないか。
滑稽にも哀れにも思える彼女の生き方が、その足跡を辿るうち、だんだん違ったものに見えてくる。人は、そんなにもかたくなに「自分自身でいる」ことが、できるものなのだろうか。他人がどう思おうと、彼女は自分の美と愛に忠実に生きたのだ。映画が進むにつれて、玉葱の皮を剥いていくように、透き通るように純粋な「美しい」生き方が姿を現す。
1995年くらいまで、彼女はクラシックな真っ白いドレスに身を包み、丁寧に化粧を施して、横浜の街角にあくまで街娼として立ち続けた。誰が見ても、歴とした「老女」である。ゆえに、お客がつくことはほとんどない。時折、昔なじみが幾ばくかのお金を手渡していたようだった。
その暮らしは、最後のほうはほぼホームレスに近かった。荷物をクリーニング屋さんに預け、決まった美容院に出入りし、昼間から夜、横浜の街を徘徊する日々。真っ白に着飾った老女がうろうろと街中を歩き回る姿は異様で、彼女は有名人だった。じろじろ見られたり、嗤われたり、店やビルからつまみ出されることも珍しくなかった。しかし彼女は超然として、決して自分が自分である事をやめなかった。
印象的だったのは、ある化粧品店のスタッフの証言だ。
メリーさんはしばしばその化粧品店にいりびたり、なにを買うでもなくしきりに、輸入化粧品や香水の美しい瓶に魅入っていた。色とりどりのガラス瓶に見とれては、きれいねえ、きれいねえ、と呟いていたという。美しい化粧品の瓶に幻影を見る、空想力と美意識が、彼女の頭の中には常に躍動していたのではないか。美しい恋、美しいドレス、美しいドラマ。彼女は誰にも見えない自分だけの美の世界を、かたくなに行き続けていたのではないか。
滑稽にも哀れにも思える彼女の生き方が、その足跡を辿るうち、だんだん違ったものに見えてくる。人は、そんなにもかたくなに「自分自身でいる」ことが、できるものなのだろうか。他人がどう思おうと、彼女は自分の美と愛に忠実に生きたのだ。映画が進むにつれて、玉葱の皮を剥いていくように、透き通るように純粋な「美しい」生き方が姿を現す。
 ある救急隊員の手記として、こんな記事を読んだことがある。
119番の要請に応じて夜中、ある家に駆けつけた。倒れたのは70代になる女性で、意識を失いかけている状態だった。担架に乗せると、彼女はほぼ意識の無い状態のまま、着ていた寝間着の裾を直そうとしたのだという。
救急隊員の青年はその仕草に、痛烈な「女性」を感じて、衝撃を受けた、と語った。その衝撃には、尊敬のような、畏怖のような、「頭の下がる思い」が含まれていたようだった。
実は、本連載の最終回は、「美とは○○である」というふうに、警句的な一文で締めたいと思っていた。しかし書き進めるうちに、この2つのエピソードが常に私の頭に、「美」のベース音のようにしてこびりついているのに気がついた。
美しくあるためには、何が美しいのかということをまず、知らなければならないのだろうと思う。でも、万人に共通の、教科書のような美というものはない。
かつて中国で小さな足が美しいという観念が広まり「纏足」が流行したと歴史で習った。しかし最近まで、私は「纏足」が実際にどんなものなのか、全く知らなかった。「纏足」とは、幼女の足指の骨を折ってしまい(!)、きつく布で巻き締める、という風習だったのだ。インターネットで検索すると、画像が出てくるので、ご興味の向きは是非、参照されたい(かなりショッキングなものなので、ご注意を)。
私たちが心のどこかで望んでいる美というのは、そんなものではないはずだ。
ならば、何を美とするのか。
ある救急隊員の手記として、こんな記事を読んだことがある。
119番の要請に応じて夜中、ある家に駆けつけた。倒れたのは70代になる女性で、意識を失いかけている状態だった。担架に乗せると、彼女はほぼ意識の無い状態のまま、着ていた寝間着の裾を直そうとしたのだという。
救急隊員の青年はその仕草に、痛烈な「女性」を感じて、衝撃を受けた、と語った。その衝撃には、尊敬のような、畏怖のような、「頭の下がる思い」が含まれていたようだった。
実は、本連載の最終回は、「美とは○○である」というふうに、警句的な一文で締めたいと思っていた。しかし書き進めるうちに、この2つのエピソードが常に私の頭に、「美」のベース音のようにしてこびりついているのに気がついた。
美しくあるためには、何が美しいのかということをまず、知らなければならないのだろうと思う。でも、万人に共通の、教科書のような美というものはない。
かつて中国で小さな足が美しいという観念が広まり「纏足」が流行したと歴史で習った。しかし最近まで、私は「纏足」が実際にどんなものなのか、全く知らなかった。「纏足」とは、幼女の足指の骨を折ってしまい(!)、きつく布で巻き締める、という風習だったのだ。インターネットで検索すると、画像が出てくるので、ご興味の向きは是非、参照されたい(かなりショッキングなものなので、ご注意を)。
私たちが心のどこかで望んでいる美というのは、そんなものではないはずだ。
ならば、何を美とするのか。
 美しくなれる薬があり、美しくなれる化粧品があり、美しくなれる服がある。少なくとも、そう考えられている。しかし、その中のどれを選べば良いのか、ということへの答えは、どこにもない。
多分、その答えを「自分以外の誰か」に求めているうちは、なかなか、「美」には近づけないのかもしれない、と私は思っている。
> 「美人の条件」記事一覧
美しくなれる薬があり、美しくなれる化粧品があり、美しくなれる服がある。少なくとも、そう考えられている。しかし、その中のどれを選べば良いのか、ということへの答えは、どこにもない。
多分、その答えを「自分以外の誰か」に求めているうちは、なかなか、「美」には近づけないのかもしれない、と私は思っている。
> 「美人の条件」記事一覧