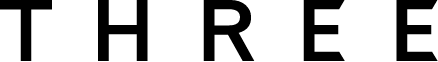#011 菊竹 寛(ギャラリスト・編集者)
日常のたった一コマが、過去の記憶を顕微鏡で覗きこむように拡大させて、胸をギュッと締めつけることがある。
 89歳を迎える祖母は、お酒とタバコと珈琲が大好きだった。
自分が着る服は自分で作り、いくつかの指輪を手放さずにつけていた。
「体が小さいから自分に似合う服がない。靴とサングラスくらいよ。デパートで買うのは」
よくそう言っていた。
今では施設で暮らし、記憶もあやふやになってきているけれど、体の隅々に刻まれた祖母の心意気は消えていない。
ずっと磨いてきた指先が綺麗だと、介護士たちに褒められて時折笑みを浮かべたりしている。
「ほら。おばあちゃんの顔、年のわりにはシワもないでしょう? 毎朝痛くなるくらい顔を引っ張って洗ってるんだ」
そんな自慢をしてきては、ザラメをたっぷり入れた珈琲を毎朝飲んでいたことを昨日のことのように思い出す。
少し前、近道をしようと新宿伊勢丹の1階を人混みを掻き分けるように早足で歩いていたとき、
祖母がずっと使っていた香水の香りがふと鼻についた。
あれ? 近くにいるのか? そう一瞬思ったけれど、そんなはずはない。きっとそのときも施設で昼寝でもしていただろう。
けれども、その瞬間、祖母と一緒によく歩いた、新宿から遠く離れた場所にあるデパートの光景がまざまざと目の前に蘇ってきて、当時の売り場の様子や店員の言動さえ見聞きできるようで、タイムワープをしたようだった。
もう2度とこの光景と同じ瞬間を生きることはないだろう—そう我にかえると、一緒に歩いた記憶が残っていることに、寂しさ半分、憎らしさ半分……。記憶など消え失せてしまえ—そんなことを考えながら歩いていると、思わず舌打ちをしてしまった。
自分の生きてきた時間のほんの一コマが、掛け替えのない大切なものになってしまうことがある。それは、そのときどきの気分はもちろん、天気にさえも左右されるものかもしれない。曖昧で、「美しい」もの。そんな小さな掛け替えのないものの寄せ集めが、いつか驚くような美の姿を作り上げてくれるのかな、なんて淡い期待を持って日々を過ごす。
記憶がない場所に、美は存在しない。美とはきっと、人の頭に、皮膚に、感覚に、刻まれた記憶が何かと衝突したときに立ち上がってくるものだと思う。
Photo by Mariko Oya
89歳を迎える祖母は、お酒とタバコと珈琲が大好きだった。
自分が着る服は自分で作り、いくつかの指輪を手放さずにつけていた。
「体が小さいから自分に似合う服がない。靴とサングラスくらいよ。デパートで買うのは」
よくそう言っていた。
今では施設で暮らし、記憶もあやふやになってきているけれど、体の隅々に刻まれた祖母の心意気は消えていない。
ずっと磨いてきた指先が綺麗だと、介護士たちに褒められて時折笑みを浮かべたりしている。
「ほら。おばあちゃんの顔、年のわりにはシワもないでしょう? 毎朝痛くなるくらい顔を引っ張って洗ってるんだ」
そんな自慢をしてきては、ザラメをたっぷり入れた珈琲を毎朝飲んでいたことを昨日のことのように思い出す。
少し前、近道をしようと新宿伊勢丹の1階を人混みを掻き分けるように早足で歩いていたとき、
祖母がずっと使っていた香水の香りがふと鼻についた。
あれ? 近くにいるのか? そう一瞬思ったけれど、そんなはずはない。きっとそのときも施設で昼寝でもしていただろう。
けれども、その瞬間、祖母と一緒によく歩いた、新宿から遠く離れた場所にあるデパートの光景がまざまざと目の前に蘇ってきて、当時の売り場の様子や店員の言動さえ見聞きできるようで、タイムワープをしたようだった。
もう2度とこの光景と同じ瞬間を生きることはないだろう—そう我にかえると、一緒に歩いた記憶が残っていることに、寂しさ半分、憎らしさ半分……。記憶など消え失せてしまえ—そんなことを考えながら歩いていると、思わず舌打ちをしてしまった。
自分の生きてきた時間のほんの一コマが、掛け替えのない大切なものになってしまうことがある。それは、そのときどきの気分はもちろん、天気にさえも左右されるものかもしれない。曖昧で、「美しい」もの。そんな小さな掛け替えのないものの寄せ集めが、いつか驚くような美の姿を作り上げてくれるのかな、なんて淡い期待を持って日々を過ごす。
記憶がない場所に、美は存在しない。美とはきっと、人の頭に、皮膚に、感覚に、刻まれた記憶が何かと衝突したときに立ち上がってくるものだと思う。
Photo by Mariko Oya
 89歳を迎える祖母は、お酒とタバコと珈琲が大好きだった。
自分が着る服は自分で作り、いくつかの指輪を手放さずにつけていた。
「体が小さいから自分に似合う服がない。靴とサングラスくらいよ。デパートで買うのは」
よくそう言っていた。
今では施設で暮らし、記憶もあやふやになってきているけれど、体の隅々に刻まれた祖母の心意気は消えていない。
ずっと磨いてきた指先が綺麗だと、介護士たちに褒められて時折笑みを浮かべたりしている。
「ほら。おばあちゃんの顔、年のわりにはシワもないでしょう? 毎朝痛くなるくらい顔を引っ張って洗ってるんだ」
そんな自慢をしてきては、ザラメをたっぷり入れた珈琲を毎朝飲んでいたことを昨日のことのように思い出す。
少し前、近道をしようと新宿伊勢丹の1階を人混みを掻き分けるように早足で歩いていたとき、
祖母がずっと使っていた香水の香りがふと鼻についた。
あれ? 近くにいるのか? そう一瞬思ったけれど、そんなはずはない。きっとそのときも施設で昼寝でもしていただろう。
けれども、その瞬間、祖母と一緒によく歩いた、新宿から遠く離れた場所にあるデパートの光景がまざまざと目の前に蘇ってきて、当時の売り場の様子や店員の言動さえ見聞きできるようで、タイムワープをしたようだった。
もう2度とこの光景と同じ瞬間を生きることはないだろう—そう我にかえると、一緒に歩いた記憶が残っていることに、寂しさ半分、憎らしさ半分……。記憶など消え失せてしまえ—そんなことを考えながら歩いていると、思わず舌打ちをしてしまった。
自分の生きてきた時間のほんの一コマが、掛け替えのない大切なものになってしまうことがある。それは、そのときどきの気分はもちろん、天気にさえも左右されるものかもしれない。曖昧で、「美しい」もの。そんな小さな掛け替えのないものの寄せ集めが、いつか驚くような美の姿を作り上げてくれるのかな、なんて淡い期待を持って日々を過ごす。
記憶がない場所に、美は存在しない。美とはきっと、人の頭に、皮膚に、感覚に、刻まれた記憶が何かと衝突したときに立ち上がってくるものだと思う。
Photo by Mariko Oya
89歳を迎える祖母は、お酒とタバコと珈琲が大好きだった。
自分が着る服は自分で作り、いくつかの指輪を手放さずにつけていた。
「体が小さいから自分に似合う服がない。靴とサングラスくらいよ。デパートで買うのは」
よくそう言っていた。
今では施設で暮らし、記憶もあやふやになってきているけれど、体の隅々に刻まれた祖母の心意気は消えていない。
ずっと磨いてきた指先が綺麗だと、介護士たちに褒められて時折笑みを浮かべたりしている。
「ほら。おばあちゃんの顔、年のわりにはシワもないでしょう? 毎朝痛くなるくらい顔を引っ張って洗ってるんだ」
そんな自慢をしてきては、ザラメをたっぷり入れた珈琲を毎朝飲んでいたことを昨日のことのように思い出す。
少し前、近道をしようと新宿伊勢丹の1階を人混みを掻き分けるように早足で歩いていたとき、
祖母がずっと使っていた香水の香りがふと鼻についた。
あれ? 近くにいるのか? そう一瞬思ったけれど、そんなはずはない。きっとそのときも施設で昼寝でもしていただろう。
けれども、その瞬間、祖母と一緒によく歩いた、新宿から遠く離れた場所にあるデパートの光景がまざまざと目の前に蘇ってきて、当時の売り場の様子や店員の言動さえ見聞きできるようで、タイムワープをしたようだった。
もう2度とこの光景と同じ瞬間を生きることはないだろう—そう我にかえると、一緒に歩いた記憶が残っていることに、寂しさ半分、憎らしさ半分……。記憶など消え失せてしまえ—そんなことを考えながら歩いていると、思わず舌打ちをしてしまった。
自分の生きてきた時間のほんの一コマが、掛け替えのない大切なものになってしまうことがある。それは、そのときどきの気分はもちろん、天気にさえも左右されるものかもしれない。曖昧で、「美しい」もの。そんな小さな掛け替えのないものの寄せ集めが、いつか驚くような美の姿を作り上げてくれるのかな、なんて淡い期待を持って日々を過ごす。
記憶がない場所に、美は存在しない。美とはきっと、人の頭に、皮膚に、感覚に、刻まれた記憶が何かと衝突したときに立ち上がってくるものだと思う。
Photo by Mariko Oya