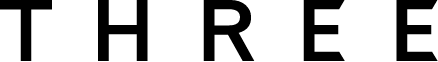#012 藤田 貴大(演劇作家)
開演時間の直前、女優たちが楽屋でさまざまな準備を忙しそうにしているのだけれど、その時間がたまらなく美しいので、あつかましいけれど女子楽屋にはかならずぼくが座る椅子を用意しておいて、彼女らが舞台に上がるまでの一部始終を観察する。
 何人かがドライヤーを当てる音が楽屋に無機質に響いていくのが、開演時間が迫ってきている緊張感を少しずつ高めていく。
スタイリストさんやもしくは共演者同士で黙々と髪型をつくっていくときに、髪をとかす音やシューっと短めのアイロンの音が細切れに聞こえてくる。
オイルやワックスの匂い。
女優の髪って一体、なにを含めたらそうなるのだろうってくらい、本当に含めているもの以上のなにかが含まれている。
それを単に、色気とかそういう言葉で片づけたくない。
もっと抽象的ななにかを込めている気がする。
顔のどこか、なにかラインをいれるとき、鏡にグッと近づく姿。
意識がすーっと、そこに集中しているのか、その瞬間は周りのことを気にすることができない。
鏡のなかの自分のそれだけに集中するときの表情ほど美しいものはないのではないか。
座席からすこしだけおしりを浮かす。
つま先がすこしだけ震えている。
気を遣えるとかいう言葉があって、気を遣えるひとは評価されるし、たしかに気を遣えることはよいことなのかもしれないが、ぼくは気を遣えることがかならずしもよいとはおもわない。
気を遣えるという言葉のなかにある、誰を対象にした気を、遣うのだろうという不気味さをおもうと、やっぱり気を遣えるという言葉はあんまり好きじゃない。
まったく気を遣っていない瞬間が、楽屋には詰まっている。
なにかを纏う時間。
これから舞台に上がって、二時間くらいの上演時間を観客の目にさらされた場所で過ごす。
自分のために自分を纏う時間が、やがてそれは観客のための時間へと広がっていく。
髪に触れる、化粧をする、衣装を着る。
ひとつひとつの手つきに、ある覚悟があって。決断があって。
そういう特別な時間をぼくは見つめていたくて、楽屋のいちばんぜんぶが見渡せる席に座る。
うっとうしいだろうが、そこに座っている。
女優がどういうものをつかって自分をつくっていくのかを観察する。
みんなそれぞれ手順がちがうのも、見ていて興味深い。
肌に色を重ねていく様子。その時間は、とても美しい。
やがていよいよ開演時間が迫ると、静寂に包まれる。
女優たちは舞台へ何も言わずに向かっていく。そして楽屋はからっぽになってしまう。
からっぽになった楽屋が、これまたよい。
さっきまでここで、彼女たちは準備をしていた。黙々と自分のために。
そして舞台に存在する嘘の時間のために。
嘘はあたかも、よくないって印象だけれど、嘘がなくちゃ生きていけない。
世界のぜんぶがじつのところ嘘であってほしいとすらおもう。
舞台にて、嘘をつく準備をさっきまでここでしていたのだ。
からっぽの楽屋。
彼女らがつく嘘ほど、美しいものはない。
何人かがドライヤーを当てる音が楽屋に無機質に響いていくのが、開演時間が迫ってきている緊張感を少しずつ高めていく。
スタイリストさんやもしくは共演者同士で黙々と髪型をつくっていくときに、髪をとかす音やシューっと短めのアイロンの音が細切れに聞こえてくる。
オイルやワックスの匂い。
女優の髪って一体、なにを含めたらそうなるのだろうってくらい、本当に含めているもの以上のなにかが含まれている。
それを単に、色気とかそういう言葉で片づけたくない。
もっと抽象的ななにかを込めている気がする。
顔のどこか、なにかラインをいれるとき、鏡にグッと近づく姿。
意識がすーっと、そこに集中しているのか、その瞬間は周りのことを気にすることができない。
鏡のなかの自分のそれだけに集中するときの表情ほど美しいものはないのではないか。
座席からすこしだけおしりを浮かす。
つま先がすこしだけ震えている。
気を遣えるとかいう言葉があって、気を遣えるひとは評価されるし、たしかに気を遣えることはよいことなのかもしれないが、ぼくは気を遣えることがかならずしもよいとはおもわない。
気を遣えるという言葉のなかにある、誰を対象にした気を、遣うのだろうという不気味さをおもうと、やっぱり気を遣えるという言葉はあんまり好きじゃない。
まったく気を遣っていない瞬間が、楽屋には詰まっている。
なにかを纏う時間。
これから舞台に上がって、二時間くらいの上演時間を観客の目にさらされた場所で過ごす。
自分のために自分を纏う時間が、やがてそれは観客のための時間へと広がっていく。
髪に触れる、化粧をする、衣装を着る。
ひとつひとつの手つきに、ある覚悟があって。決断があって。
そういう特別な時間をぼくは見つめていたくて、楽屋のいちばんぜんぶが見渡せる席に座る。
うっとうしいだろうが、そこに座っている。
女優がどういうものをつかって自分をつくっていくのかを観察する。
みんなそれぞれ手順がちがうのも、見ていて興味深い。
肌に色を重ねていく様子。その時間は、とても美しい。
やがていよいよ開演時間が迫ると、静寂に包まれる。
女優たちは舞台へ何も言わずに向かっていく。そして楽屋はからっぽになってしまう。
からっぽになった楽屋が、これまたよい。
さっきまでここで、彼女たちは準備をしていた。黙々と自分のために。
そして舞台に存在する嘘の時間のために。
嘘はあたかも、よくないって印象だけれど、嘘がなくちゃ生きていけない。
世界のぜんぶがじつのところ嘘であってほしいとすらおもう。
舞台にて、嘘をつく準備をさっきまでここでしていたのだ。
からっぽの楽屋。
彼女らがつく嘘ほど、美しいものはない。
 何人かがドライヤーを当てる音が楽屋に無機質に響いていくのが、開演時間が迫ってきている緊張感を少しずつ高めていく。
スタイリストさんやもしくは共演者同士で黙々と髪型をつくっていくときに、髪をとかす音やシューっと短めのアイロンの音が細切れに聞こえてくる。
オイルやワックスの匂い。
女優の髪って一体、なにを含めたらそうなるのだろうってくらい、本当に含めているもの以上のなにかが含まれている。
それを単に、色気とかそういう言葉で片づけたくない。
もっと抽象的ななにかを込めている気がする。
顔のどこか、なにかラインをいれるとき、鏡にグッと近づく姿。
意識がすーっと、そこに集中しているのか、その瞬間は周りのことを気にすることができない。
鏡のなかの自分のそれだけに集中するときの表情ほど美しいものはないのではないか。
座席からすこしだけおしりを浮かす。
つま先がすこしだけ震えている。
気を遣えるとかいう言葉があって、気を遣えるひとは評価されるし、たしかに気を遣えることはよいことなのかもしれないが、ぼくは気を遣えることがかならずしもよいとはおもわない。
気を遣えるという言葉のなかにある、誰を対象にした気を、遣うのだろうという不気味さをおもうと、やっぱり気を遣えるという言葉はあんまり好きじゃない。
まったく気を遣っていない瞬間が、楽屋には詰まっている。
なにかを纏う時間。
これから舞台に上がって、二時間くらいの上演時間を観客の目にさらされた場所で過ごす。
自分のために自分を纏う時間が、やがてそれは観客のための時間へと広がっていく。
髪に触れる、化粧をする、衣装を着る。
ひとつひとつの手つきに、ある覚悟があって。決断があって。
そういう特別な時間をぼくは見つめていたくて、楽屋のいちばんぜんぶが見渡せる席に座る。
うっとうしいだろうが、そこに座っている。
女優がどういうものをつかって自分をつくっていくのかを観察する。
みんなそれぞれ手順がちがうのも、見ていて興味深い。
肌に色を重ねていく様子。その時間は、とても美しい。
やがていよいよ開演時間が迫ると、静寂に包まれる。
女優たちは舞台へ何も言わずに向かっていく。そして楽屋はからっぽになってしまう。
からっぽになった楽屋が、これまたよい。
さっきまでここで、彼女たちは準備をしていた。黙々と自分のために。
そして舞台に存在する嘘の時間のために。
嘘はあたかも、よくないって印象だけれど、嘘がなくちゃ生きていけない。
世界のぜんぶがじつのところ嘘であってほしいとすらおもう。
舞台にて、嘘をつく準備をさっきまでここでしていたのだ。
からっぽの楽屋。
彼女らがつく嘘ほど、美しいものはない。
何人かがドライヤーを当てる音が楽屋に無機質に響いていくのが、開演時間が迫ってきている緊張感を少しずつ高めていく。
スタイリストさんやもしくは共演者同士で黙々と髪型をつくっていくときに、髪をとかす音やシューっと短めのアイロンの音が細切れに聞こえてくる。
オイルやワックスの匂い。
女優の髪って一体、なにを含めたらそうなるのだろうってくらい、本当に含めているもの以上のなにかが含まれている。
それを単に、色気とかそういう言葉で片づけたくない。
もっと抽象的ななにかを込めている気がする。
顔のどこか、なにかラインをいれるとき、鏡にグッと近づく姿。
意識がすーっと、そこに集中しているのか、その瞬間は周りのことを気にすることができない。
鏡のなかの自分のそれだけに集中するときの表情ほど美しいものはないのではないか。
座席からすこしだけおしりを浮かす。
つま先がすこしだけ震えている。
気を遣えるとかいう言葉があって、気を遣えるひとは評価されるし、たしかに気を遣えることはよいことなのかもしれないが、ぼくは気を遣えることがかならずしもよいとはおもわない。
気を遣えるという言葉のなかにある、誰を対象にした気を、遣うのだろうという不気味さをおもうと、やっぱり気を遣えるという言葉はあんまり好きじゃない。
まったく気を遣っていない瞬間が、楽屋には詰まっている。
なにかを纏う時間。
これから舞台に上がって、二時間くらいの上演時間を観客の目にさらされた場所で過ごす。
自分のために自分を纏う時間が、やがてそれは観客のための時間へと広がっていく。
髪に触れる、化粧をする、衣装を着る。
ひとつひとつの手つきに、ある覚悟があって。決断があって。
そういう特別な時間をぼくは見つめていたくて、楽屋のいちばんぜんぶが見渡せる席に座る。
うっとうしいだろうが、そこに座っている。
女優がどういうものをつかって自分をつくっていくのかを観察する。
みんなそれぞれ手順がちがうのも、見ていて興味深い。
肌に色を重ねていく様子。その時間は、とても美しい。
やがていよいよ開演時間が迫ると、静寂に包まれる。
女優たちは舞台へ何も言わずに向かっていく。そして楽屋はからっぽになってしまう。
からっぽになった楽屋が、これまたよい。
さっきまでここで、彼女たちは準備をしていた。黙々と自分のために。
そして舞台に存在する嘘の時間のために。
嘘はあたかも、よくないって印象だけれど、嘘がなくちゃ生きていけない。
世界のぜんぶがじつのところ嘘であってほしいとすらおもう。
舞台にて、嘘をつく準備をさっきまでここでしていたのだ。
からっぽの楽屋。
彼女らがつく嘘ほど、美しいものはない。