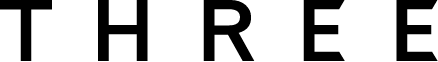Q. 「人間としての『美しさ』は、どんなところに表れると思いますか?」
「人間としての『美しさ』」。
それはいったい、どのようなものだろう。
決して、つるっとした毛の生えていない肌や、長い足で二足歩行をしている、などということではないだろう。少なくとも、この設問はそのようには前提していないだろう。
おそらくこの質問は、「人間の精神的な美は、外見にも表れるはずだ」という思想に立っている。
全体的に、とはいかなくても「心が美しければ姿にもどこかしら美しく見えるところがあるはずだ」という前提のもとに、この質問は生まれている。
でも、ほんとうにそうだろうか。
すくなくとも私には、この説は、あまり積極的には、信じられない。
その逆の、いわば「心は限りなく美しいけれど、姿形はあくまで醜い」人間も、いるかもしれないと私は思う。
天使のように美しい悪魔は、多分、ごまんといる。
とはいえ、もう少し「人間としての美しさ」について、考えてみる。
仮に、ある人の姿や立ち居振る舞いを「美しい」と感じる人がたくさんいたとする。
たとえば、あるバレリーナの踊りがそうだとしよう。
彼女は優雅なコスチュームを身に纏い、鍛え上げた肉体を重力に反抗して凛と立たせ、空を飛翔するように跳躍する。
この衣装やポーズや動きは、彼女が細心に「創造した」ものだ。
バレエのレッスン場には、かならず、大きな鏡がある。
ダンサーたちは、その鏡の中に、「今の自分」を見なければならない。
どんなに下手でも、不格好でも、それを見なければならない。
そして、より「美しく」なるよう、修正を重ねていくのだ。
では「より美しいかたち」は、どこにあるだろう?
それは、バレリーナの頭の中、指導する人々の頭の中にある。
バレエのような複雑なことでなくとも、私たちは「自分の姿」をチェックする。
どんなブティックでも、どんなコスメショップでも、必ず、鏡がある。
私たちは鏡を見る。
そして、頭の中にある「美」のイメージに、自分を少しでも近づけようとする。
時には、他人の評価を受ける。
肥ったとか痩せたとか言われ、一喜一憂する。
この場合、他人の評価もまた、一つの「鏡の中の自分」となる。
だが、頭の中にある「美」のイメージとは、どうやってできたのだろう。
いったいどこから「美」は、頭の中に入り込み、棲みつくのだろう。
平安時代にはぽっちゃりしたおたふく顔で、針のような切れ長の目が美人の条件だったそうだ。
大正時代に「絶世の美女」と言われた女性の顔写真を見たことがあるが、面長で、やはり細めの切れ長の目をしていた。
今では「プチ整形」して目をぱっちりと大きくする人も少なくない。顔も身体も細く小さいほど「美しい」とされる。
ことほど左様に、「美」のイメージはどんどん変わってしまう。
濃く眉を引く「美人」がいる時代もあれば、眉など剃って「美人」になる時代もある。
胸をさらしで巻きしめる時代がある一方で、胸の中にシリコンを入れて膨らます時代がある。
めまぐるしい流行廃りの中で、私たちの「美意識」は簡単に描き換えられていく。
こう考えてくると、「美」とはなにか、よくわからなくなってしまう。
でも、少なくとも一つ、カギのように思えることがある。
それは、「美」のイメージがどんな像か、とは関係がない。
美しくなろうとする人は、多かれ少なかれ「鏡の中の自分を見て、頭の中の『美』のイメージと照らしあわせ、現実の自分の姿を修正していく」ということである。
立ち居振る舞いにしても、化粧や服装にしても、まず「理想」を抱き、「理想」に照らして自分の「すがた」をかえりみている、ということなのだ。
実際、鏡に映った自分を見ることは、あまり楽しいことではないのである。
もちろん、ギリシャ神話のナルシスよろしく、鏡の中の自分にうっとりと惚れ込める人もいるかもしれない。
だが、多くの人にとって、頭の中の「美」のイメージが美しければ美しいほど、鏡の中の現実は、心を傷つけてくるものだろうと思う。
ファッションモデルたちが「私には容姿のコンプレックスがたくさんある」と告白することからも、それは想像できる。
誰よりも鏡を見る人々は、誰よりも自分の現実の姿に傷つけられるのである。
不格好な生身の自分をまず、認めて、心をぐっさりと傷つけられるところから、「イメージに近づけていく修正」は、スタートする。
この辛い作業を何度も何度も重ねた人だけが、頭の中の「美」のイメージに限りなく近づくことができるだろう。
そんな作業はそれこそ、人間しかやらない。
現実という痛みを引き受けるのは、なみたいていのことではない。
だから、多くの人が人生のどこかで、真剣に鏡を見つめることをやめる。
そして、修正もやめる。
頭の中の「美」のイメージに近づこうとすることをやめるのだ。
若さが「美しい」と感じられるのは、生殖に適しているかどうかを知らせる、生物としての、どうしようもないセンサーだ。
ゆえに、年齢をかさねるにつれ、私たちは鏡を見るのが辛くなる。
そこに映っているものが醜く思えて仕方が無いからだ。
でも、世の中には、鏡を見ることをやめない、強い人たちがいる。
もちろん、その動機は、きれいごとだけではないかもしれない。
執念とか、嫉妬や依存のような、あまり前向きではない思いが動機になっている可能性もある。
しかしとにかく、その人たちは現実の自分を目の当たりにする痛みを、引き受ける。
多分、姿形だけでなく、自分の醜い心のあり方についても、そのようなことができるとするなら、それはまさに「人間としての『美しさ』」と言わねばならない、かもしれない。
その人の中に、苦しんでもいい、と思えるほどの情熱や動機があって、それらが美しくなるための努力に繋がったのだ。
内面的なものと、外見の美とに、何かしら繋がりがあると言えるとすれば、そういうことなのだろうと思う。
その美しい人は、おそらくは、苦しんだのだ。
 Q. 「人間としての『美しさ』は、どんなところに表れると思いますか?」
「人間としての『美しさ』」。
それはいったい、どのようなものだろう。
決して、つるっとした毛の生えていない肌や、長い足で二足歩行をしている、などということではないだろう。少なくとも、この設問はそのようには前提していないだろう。
おそらくこの質問は、「人間の精神的な美は、外見にも表れるはずだ」という思想に立っている。
全体的に、とはいかなくても「心が美しければ姿にもどこかしら美しく見えるところがあるはずだ」という前提のもとに、この質問は生まれている。
でも、ほんとうにそうだろうか。
すくなくとも私には、この説は、あまり積極的には、信じられない。
その逆の、いわば「心は限りなく美しいけれど、姿形はあくまで醜い」人間も、いるかもしれないと私は思う。
天使のように美しい悪魔は、多分、ごまんといる。
とはいえ、もう少し「人間としての美しさ」について、考えてみる。
仮に、ある人の姿や立ち居振る舞いを「美しい」と感じる人がたくさんいたとする。
たとえば、あるバレリーナの踊りがそうだとしよう。
彼女は優雅なコスチュームを身に纏い、鍛え上げた肉体を重力に反抗して凛と立たせ、空を飛翔するように跳躍する。
この衣装やポーズや動きは、彼女が細心に「創造した」ものだ。
バレエのレッスン場には、かならず、大きな鏡がある。
ダンサーたちは、その鏡の中に、「今の自分」を見なければならない。
どんなに下手でも、不格好でも、それを見なければならない。
そして、より「美しく」なるよう、修正を重ねていくのだ。
では「より美しいかたち」は、どこにあるだろう?
それは、バレリーナの頭の中、指導する人々の頭の中にある。
バレエのような複雑なことでなくとも、私たちは「自分の姿」をチェックする。
どんなブティックでも、どんなコスメショップでも、必ず、鏡がある。
私たちは鏡を見る。
そして、頭の中にある「美」のイメージに、自分を少しでも近づけようとする。
時には、他人の評価を受ける。
肥ったとか痩せたとか言われ、一喜一憂する。
この場合、他人の評価もまた、一つの「鏡の中の自分」となる。
だが、頭の中にある「美」のイメージとは、どうやってできたのだろう。
いったいどこから「美」は、頭の中に入り込み、棲みつくのだろう。
平安時代にはぽっちゃりしたおたふく顔で、針のような切れ長の目が美人の条件だったそうだ。
大正時代に「絶世の美女」と言われた女性の顔写真を見たことがあるが、面長で、やはり細めの切れ長の目をしていた。
今では「プチ整形」して目をぱっちりと大きくする人も少なくない。顔も身体も細く小さいほど「美しい」とされる。
ことほど左様に、「美」のイメージはどんどん変わってしまう。
濃く眉を引く「美人」がいる時代もあれば、眉など剃って「美人」になる時代もある。
胸をさらしで巻きしめる時代がある一方で、胸の中にシリコンを入れて膨らます時代がある。
めまぐるしい流行廃りの中で、私たちの「美意識」は簡単に描き換えられていく。
こう考えてくると、「美」とはなにか、よくわからなくなってしまう。
でも、少なくとも一つ、カギのように思えることがある。
それは、「美」のイメージがどんな像か、とは関係がない。
美しくなろうとする人は、多かれ少なかれ「鏡の中の自分を見て、頭の中の『美』のイメージと照らしあわせ、現実の自分の姿を修正していく」ということである。
立ち居振る舞いにしても、化粧や服装にしても、まず「理想」を抱き、「理想」に照らして自分の「すがた」をかえりみている、ということなのだ。
実際、鏡に映った自分を見ることは、あまり楽しいことではないのである。
もちろん、ギリシャ神話のナルシスよろしく、鏡の中の自分にうっとりと惚れ込める人もいるかもしれない。
だが、多くの人にとって、頭の中の「美」のイメージが美しければ美しいほど、鏡の中の現実は、心を傷つけてくるものだろうと思う。
ファッションモデルたちが「私には容姿のコンプレックスがたくさんある」と告白することからも、それは想像できる。
誰よりも鏡を見る人々は、誰よりも自分の現実の姿に傷つけられるのである。
不格好な生身の自分をまず、認めて、心をぐっさりと傷つけられるところから、「イメージに近づけていく修正」は、スタートする。
この辛い作業を何度も何度も重ねた人だけが、頭の中の「美」のイメージに限りなく近づくことができるだろう。
そんな作業はそれこそ、人間しかやらない。
現実という痛みを引き受けるのは、なみたいていのことではない。
だから、多くの人が人生のどこかで、真剣に鏡を見つめることをやめる。
そして、修正もやめる。
頭の中の「美」のイメージに近づこうとすることをやめるのだ。
若さが「美しい」と感じられるのは、生殖に適しているかどうかを知らせる、生物としての、どうしようもないセンサーだ。
ゆえに、年齢をかさねるにつれ、私たちは鏡を見るのが辛くなる。
そこに映っているものが醜く思えて仕方が無いからだ。
でも、世の中には、鏡を見ることをやめない、強い人たちがいる。
もちろん、その動機は、きれいごとだけではないかもしれない。
執念とか、嫉妬や依存のような、あまり前向きではない思いが動機になっている可能性もある。
しかしとにかく、その人たちは現実の自分を目の当たりにする痛みを、引き受ける。
多分、姿形だけでなく、自分の醜い心のあり方についても、そのようなことができるとするなら、それはまさに「人間としての『美しさ』」と言わねばならない、かもしれない。
その人の中に、苦しんでもいい、と思えるほどの情熱や動機があって、それらが美しくなるための努力に繋がったのだ。
内面的なものと、外見の美とに、何かしら繋がりがあると言えるとすれば、そういうことなのだろうと思う。
その美しい人は、おそらくは、苦しんだのだ。
Q. 「人間としての『美しさ』は、どんなところに表れると思いますか?」
「人間としての『美しさ』」。
それはいったい、どのようなものだろう。
決して、つるっとした毛の生えていない肌や、長い足で二足歩行をしている、などということではないだろう。少なくとも、この設問はそのようには前提していないだろう。
おそらくこの質問は、「人間の精神的な美は、外見にも表れるはずだ」という思想に立っている。
全体的に、とはいかなくても「心が美しければ姿にもどこかしら美しく見えるところがあるはずだ」という前提のもとに、この質問は生まれている。
でも、ほんとうにそうだろうか。
すくなくとも私には、この説は、あまり積極的には、信じられない。
その逆の、いわば「心は限りなく美しいけれど、姿形はあくまで醜い」人間も、いるかもしれないと私は思う。
天使のように美しい悪魔は、多分、ごまんといる。
とはいえ、もう少し「人間としての美しさ」について、考えてみる。
仮に、ある人の姿や立ち居振る舞いを「美しい」と感じる人がたくさんいたとする。
たとえば、あるバレリーナの踊りがそうだとしよう。
彼女は優雅なコスチュームを身に纏い、鍛え上げた肉体を重力に反抗して凛と立たせ、空を飛翔するように跳躍する。
この衣装やポーズや動きは、彼女が細心に「創造した」ものだ。
バレエのレッスン場には、かならず、大きな鏡がある。
ダンサーたちは、その鏡の中に、「今の自分」を見なければならない。
どんなに下手でも、不格好でも、それを見なければならない。
そして、より「美しく」なるよう、修正を重ねていくのだ。
では「より美しいかたち」は、どこにあるだろう?
それは、バレリーナの頭の中、指導する人々の頭の中にある。
バレエのような複雑なことでなくとも、私たちは「自分の姿」をチェックする。
どんなブティックでも、どんなコスメショップでも、必ず、鏡がある。
私たちは鏡を見る。
そして、頭の中にある「美」のイメージに、自分を少しでも近づけようとする。
時には、他人の評価を受ける。
肥ったとか痩せたとか言われ、一喜一憂する。
この場合、他人の評価もまた、一つの「鏡の中の自分」となる。
だが、頭の中にある「美」のイメージとは、どうやってできたのだろう。
いったいどこから「美」は、頭の中に入り込み、棲みつくのだろう。
平安時代にはぽっちゃりしたおたふく顔で、針のような切れ長の目が美人の条件だったそうだ。
大正時代に「絶世の美女」と言われた女性の顔写真を見たことがあるが、面長で、やはり細めの切れ長の目をしていた。
今では「プチ整形」して目をぱっちりと大きくする人も少なくない。顔も身体も細く小さいほど「美しい」とされる。
ことほど左様に、「美」のイメージはどんどん変わってしまう。
濃く眉を引く「美人」がいる時代もあれば、眉など剃って「美人」になる時代もある。
胸をさらしで巻きしめる時代がある一方で、胸の中にシリコンを入れて膨らます時代がある。
めまぐるしい流行廃りの中で、私たちの「美意識」は簡単に描き換えられていく。
こう考えてくると、「美」とはなにか、よくわからなくなってしまう。
でも、少なくとも一つ、カギのように思えることがある。
それは、「美」のイメージがどんな像か、とは関係がない。
美しくなろうとする人は、多かれ少なかれ「鏡の中の自分を見て、頭の中の『美』のイメージと照らしあわせ、現実の自分の姿を修正していく」ということである。
立ち居振る舞いにしても、化粧や服装にしても、まず「理想」を抱き、「理想」に照らして自分の「すがた」をかえりみている、ということなのだ。
実際、鏡に映った自分を見ることは、あまり楽しいことではないのである。
もちろん、ギリシャ神話のナルシスよろしく、鏡の中の自分にうっとりと惚れ込める人もいるかもしれない。
だが、多くの人にとって、頭の中の「美」のイメージが美しければ美しいほど、鏡の中の現実は、心を傷つけてくるものだろうと思う。
ファッションモデルたちが「私には容姿のコンプレックスがたくさんある」と告白することからも、それは想像できる。
誰よりも鏡を見る人々は、誰よりも自分の現実の姿に傷つけられるのである。
不格好な生身の自分をまず、認めて、心をぐっさりと傷つけられるところから、「イメージに近づけていく修正」は、スタートする。
この辛い作業を何度も何度も重ねた人だけが、頭の中の「美」のイメージに限りなく近づくことができるだろう。
そんな作業はそれこそ、人間しかやらない。
現実という痛みを引き受けるのは、なみたいていのことではない。
だから、多くの人が人生のどこかで、真剣に鏡を見つめることをやめる。
そして、修正もやめる。
頭の中の「美」のイメージに近づこうとすることをやめるのだ。
若さが「美しい」と感じられるのは、生殖に適しているかどうかを知らせる、生物としての、どうしようもないセンサーだ。
ゆえに、年齢をかさねるにつれ、私たちは鏡を見るのが辛くなる。
そこに映っているものが醜く思えて仕方が無いからだ。
でも、世の中には、鏡を見ることをやめない、強い人たちがいる。
もちろん、その動機は、きれいごとだけではないかもしれない。
執念とか、嫉妬や依存のような、あまり前向きではない思いが動機になっている可能性もある。
しかしとにかく、その人たちは現実の自分を目の当たりにする痛みを、引き受ける。
多分、姿形だけでなく、自分の醜い心のあり方についても、そのようなことができるとするなら、それはまさに「人間としての『美しさ』」と言わねばならない、かもしれない。
その人の中に、苦しんでもいい、と思えるほどの情熱や動機があって、それらが美しくなるための努力に繋がったのだ。
内面的なものと、外見の美とに、何かしら繋がりがあると言えるとすれば、そういうことなのだろうと思う。
その美しい人は、おそらくは、苦しんだのだ。