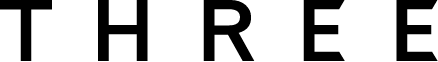#006 2019 FEBRUARY-MARCH “LOVE”

Kouichi Tabata “one way or another (red nails)”
2016, Oil on wooden panel, 30 x 45 cm
とてもざっくり言いますと、かつて絵画は教会へ設置され祈りの要素とするためや、ごく限られた人々の肖像を後世に伝えるために描かれていました。画家はあくまでも発注された絵を描く技術者として存在する、いわば匿名の存在だったのです。(もちろん絵画の歴史を振り返るならば、この認識に留まらない名画も多数存在していますし、重要な画家を考え出すと枚挙にいとまがない、ということは書き加えておきます。)
そうした絵画と画家の立ち位置も、時代ごとにどんどん変化していきます。今もそうした変化の途上にあるわけですが、歴史上、画家が匿名の技術者であることからひとりのアーティストとなり、絵画が絵画そのもののために存在し始めた、そのメルクマールとしてよく挙げられるのが、ベラスケスの作品「ラス・メニーナス」です。
この作品をめぐっては何百年にも渡って様々な面白いことが言われ続けていますので、ご興味をお持ちの方は是非ご覧いただきたいと思いますが、これまたざっくり言いますと、長らくに渡って権威の象徴として描かれていた、発注主たる王と王妃がどんっと中央に描かれておらず(むしろ彼らは画家の背後に掛けられた鏡に小さく写っているだけです)、描かれることはほぼ無かった女官や犬たちが描かれ、さらに決してキャンバスに登場することの無かった画家自身が描かれているのです。王と王妃が、画家やその周囲にいる人々を眺めるようなアングルで絵が構成されており、その他にも絵の世界を多層的に見せる仕掛けがあちこちにあるのが「ラス・メニーナス」です。
以後、絵画をキャンバスという限られた面のなかで如何にして生成し、発注者に留まらない無数の観賞者に差し出していくのかという、寄る辺のない、けれどもチャレンジングな歴史を絵画は歩みだしていくことになりました。(これもまたひとつの認識の在り方で、ラスコーの壁画まで遡って絵画の在り方を考えたりすることもあり、絵画の歴史の豊かさを考え出すと一人の人間の一生では抱えきれそうにもない、ということも書き加えておきます。念のため。)
さてここで、今回ご紹介する田幡浩一さんの作品「one way or another (red nails)」を見てみましょう。赤いマニキュアを指先にまさに今塗っているような様子が描かれています。絵を描くために用いる手と指が描かれていることから、絵画そのものに言及する「画中画の」ような要素もありつつ、机にのびる影がマニキュアを塗る指の動きや時間の移ろいを感じさせます。マニキュアを塗られた指は、この後何に触れるのだろう? コーヒーカップ? ワイングラス? 恋人の頬? などと、その先の時間を思わず想像させてくれるのも、この絵画の魅力のひとつでしょう。
さらに、この絵画作品はご覧の通りズレています。これは田幡さんが、2枚の木枠を上下に数センチずつズラして描き、作品を完成させるときにガチャッと正四角形に戻すことで生じるズレです。最終的に正四角形に戻されるまで、作品がどのような姿になるかを正確に把握することはできません。画家が完全にはコントロールし得ない偶然性も、この作品には潜んでいるのです。
今の世界において、画家は、絵画は、どのようにして存在可能でしょうか? 絵画の歴史の突端部分である今、田幡さんの作品と「ラス・メニーナス」を並べてみると、面白いことがたくさん考えられそうですし、田幡さんの作品は絵画の歴史を知ることでより深く感受することができるはすですので、冒頭長くなりましたが、「ラス・メニーナス」にも触れてみたのでした。(是非検索して見てみてください。実物はプラド美術館にあります。)
今、この世界にはアートという言葉で形容されるものが溢れています。まさに玉石混交なわけですが、これは非常に面白いことだと個人的には感じています。あらゆるアート作品やアーティストがどのように存在しているのか、20年前に比べても圧倒的に知りやすくなりました。どのアート作品やアーティストが、誰にとって玉であり、どこにおいては石でしかないのか、厳しいジャッジを日々受けながら存在せざるをえないことから、緊張感も並々ならぬものがあり、刺激的です。ときにそんな緊張感を悠々と越えた天才もいるものですが、実際には滅多にいません。緊張感もないままにアート作品やアーティストと自称/形容されるとしたら、恐らくそれはアートでもアーティストでもないでしょう。
この連載の初回で画家・五木田智央さんの作品を紹介したときにも触れましたが、良い絵には、支持体の隅々までコントロールされた画力が必須です。その上で、作品に描かれたことが、どのように外部(歴史や今の様々な事象など)と関係性を築いていくことができるのかが、優れたアート作品の核心でもあります。この田幡さんの作品は、30x45cmと小さいサイズながら、隅々まで繊細にコントロールされ、圧倒的な画力で描かれています。そのままでも十二分に成立する絵を敢えてズラし、イメージに亀裂を入れることで完成されるこの絵。そこには、田幡さんの絵画に対する愛を思わず感じてしまいます。絵画の歴史に精通したアイデアと、圧倒的な画力をもって、この手に取って眺められるくらい小さな絵を描き、少しズラしてみることで、今までに存在しなかった絵画の姿へと作品を連れていったその行為からは、絵画への野心というよりも愛をつい感じてしまうのです。そこからは、例えば、メイクをしなくとも完璧に成り立つ少女に母親がチークを塗ってあげるような、そんな場面がフと浮かぶのでした。
アート作品とアーティストは切り離されたものでは決してありません。文学の理論だったり哲学史を紐解くと、作品とアーティストとは切り離して評価すべき、という考え方もあるようですが、今を生き、制作を続けるアーティストの生身の姿からは、必ずしも理論で語れない部分がたくさんよみとれるのです。そして、その両者を繋ぐ最たるもののひとつが愛であるとも言えるでしょう。ベルリンに長く住み、そこで絵画について考え、制作を続ける田幡さんの作品を眺めていると、作家と作品を繋ぐものについて考え、「愛か…」と呟いてしまい、そしてまた両者を深く信じたくなってしまうのです。
いつもよりちょっと遠回りしつつ話題が多岐に渡ってしまいましたが、愛へのアプローチとはそんなものかもしれません。歴史を知り、対象を理解しようとしてもスルリと逃げて行ってしまうような、そんなもの。作品の解釈とも似たところが多いようです。ここで書いたことだけでは何ら愛に到達できるはずもありませんが、また次号からも愛を紡ぐことを胸に。
2016, Oil on wooden panel, 30 x 45 cm
〈作家情報〉 田幡 浩一 KOUICHI TABA
1979年栃木県生まれ。2004年に東京藝術大学美術学部先端芸術表現科卒業後、2006年に同大学大学院美術研究科油画専攻を修了。2011年より公益財団法人ポーラ美術振興財団在外研修助成などを得て、現在はベルリンを拠点に活動。 動的な要素を含む絵画作品や、絵画的制約をもって構成される映像作品などを制作。代表作に、ペンのインクがなくなるまで蜂を描き続け、それを素材に映像作品とした《bee》(2006年)、ひとつのモチーフを2つの支持体にまたがって描き、それを「ずらす」ことで完成されるドローイングと油彩作品によるシリーズ「one way or another」などがある。 http://kouichitabata.net/
〈キュレーション・執筆〉 菊竹 寛 YUTAKA KIKUTAKE
1982年生まれ。ギャラリー勤務を経て、2015年夏にYutaka Kikutake Gallery を六本木に開廊。Nerhol、平川紀道、田幡浩一など、これからのコンテンポラリーアートを切り開いていく気鋭のアーティストたちを紹介。生活文化誌「疾駆/chic」の発行・編集長も務め、ギャラリーと出版という2つの場を軸に芸術と社会の繋がりをより太く、より豊かにするようなプロジェクトに挑戦中。 www.ykggallery.com