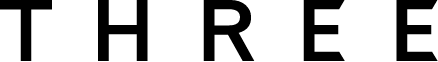#007 2019 APRIL-MAY “COLORS”



Hirofumi Isoya
“Flowers” 2015, C print & Painted frame, 35.3 x 26.6 x 3 cm
“Answer” 2013-2018, Pigment print & Painted frame, 35.3 x 25.3 x 3 cm
“Flesh Light” 2018, Pigment print & Painted frame, 35.3 x 25.3 x 3 cm
葉が茂るプランターに花柄のハンカチを添えて写真を撮り、3辺は白く、残りの1辺はピンク色に塗った額縁に入れて、「Flowers」とタイトルを付ける。
見事に噛みこんだストローをカップにさしたまま偶然か意図的か鏡にも写り込んでいるその情景を写真に撮り、3辺は白く、残りの1辺は緑色に塗った額縁に入れて、「Answer」とタイトルを付ける。
何やら薄い物体を奥の方でプリズムのように揺らめく光に透かして写真を撮り、3辺は白く、残りの1辺は赤色に塗った額縁に入れて、「Flesh Light」とタイトルを付ける。
額縁のサイズはどれも縦横30センチと20センチくらい。小さいながら、とても洗練された風合のこの作品を制作したのはアーティストの磯谷博史さんです。
磯谷さんは、あるルールに基づいてこれらの作品を制作しました。とてもシンプルなルールです。カラーで撮った写真を白黒でプリントし、写真のなかのメインモチーフの色を額縁の1辺に塗る、と。「Flowers」ではハンカチの花柄の花の色が、「Answer」では噛まれたストローの色が、「Flesh Light」では生ハム(光に透かされていたのはなんとハム!)の色が、それぞれ塗られているのです。
一般的に写真作品で作り手であるアーティストが重視するのは、まずなによりも何を撮るのか。そして、撮影したフィルムあるいはデータを、どの程度のサイズにプリントすることで、写真の中身の見え方をコントロールしどのような意味を見出していくか、です。その場合、どのような額縁に入れるのかは、アーティストが指定することもありますが、作品の発表会場や購入者にお任せということも意外と多く、作品の仕上げという意味ではそこまで優先度の高いものでない場合も多々あります。(美術館やギャラリーを訪れると、写真を目にすることも多いと思います。作品に額の造作が影響していることもよくありますので、是非気に留めて見てみてください。)
さて、その意味では、磯谷さんの作品は、写真作品の一般的な在り方とは違うベクトルへ向かう要素が溢れていると言えるでしょう。作品に登場する写真たちは、ほとんどがケータイのカメラを用いて、磯谷さんの日常のなかでのフとした瞬間に遊び心混じりに撮られているものたちです。街にあった植え込みにたまたま持っていた花柄のハンカチを添えて文字通り花を咲かせてみる。飲んでたいたときに一体何が起きていたのか心配になるくらい噛まれたストローを鏡に写すことで茶化して?みる。食べていた生ハムを光に照らしてキレイな葉の標本のようなものを出現させる。そして、それらをあえて白黒の写真でプリントし、写真の核心部分が持っていた色を額に塗って作品を仕上げるのです。
「Flowers」というタイトルからは、フラワー“ズ”と複数形であるがゆえ、ついハンカチの花模様ひとつひとつを目で追ってしまい、額縁のピンク色に可憐な心地を誘われます。「Answer」というタイトルからは、ストローを噛みながら何か難解な問いに答えようとしていたのではないか?こんなに噛むほど過酷な問いに?と冗談めいたユーモアを感じさせられます。そして「Flesh Light」というタイトルからは、葉脈のような謎の物体が放つ美しい光が、実は生ハムのFleshであったというオチとともに軽めのクスッとした笑いが導かれます。
磯谷さんのこれらの作品は、記憶に名前と、そして色を添えるような行為と言えるかもしれません。ケータイに撮り溜められた様々な写真を見返しながら、作品にする写真を選んでいくと磯谷さんは言います。日々を過ごすなかで忘れていたことや、はたまた忘れ得ないような瞬間から色を抜き、再び色を添えて、形を与える。頭のなかでは誰しもが日々行っているかもしれないことを作品として完成させるまでのステップには、磯谷さんの日常のいくつかの層があり、それらがエレガントに織りなされていくのです。
「あのときに起きていたことの核心はなんだっただろう?」「その瞬間一番印象的だった色は?」「この場面に自分だったらどんなタイトルを付けてみようか?」などなど自身の体験にもフィードバックさせてみるとどうでしょう? これらの作品が生まれてくる過程とルールは、日々の時間の層や記憶たちにいつもと異なる輝きを与えてくれるようです。
〈作家情報〉 磯谷博史 HIROFUMI ISOYA
1978年生まれ。美術家。東京藝術大学建築科を卒業後、同大学大学院先端芸術表現科および、ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ、アソシエイトリサーチプログラムで美術を学ぶ。彫刻、写真、ドローイング、それら相互の関わりを通して、認識の一貫性や、統合的な時間感覚を再考する。森美術館で開催中の展覧会「六本木クロッシング2019展:つないでみる」に出展中。 http://www.whoisisoya.com/
〈キュレーション・執筆〉 菊竹 寛 YUTAKA KIKUTAKE
1982年生まれ。ギャラリー勤務を経て、2015年夏にYutaka Kikutake Gallery を六本木に開廊。Nerhol、平川紀道、田幡浩一など、これからのコンテンポラリーアートを切り開いていく気鋭のアーティストたちを紹介。生活文化誌「疾駆/chic」の発行・編集長も務め、ギャラリーと出版という2つの場を軸に芸術と社会の繋がりをより太く、より豊かにするようなプロジェクトに挑戦中。 www.ykggallery.com